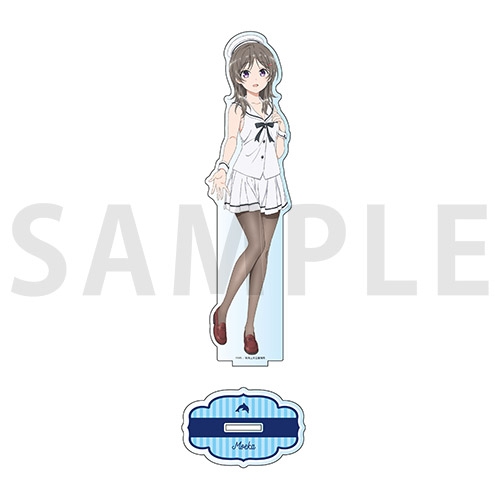331話 侵攻19
331話 侵攻19
視線で制止されたように感じたカレンが問い掛ける。
「止められた気がしたのですが、私の勘違いでしょうか?」
「いいえ、勘違いではありませんよ。」
「では・・・どういうつもりです?」
一刻も早く情報を伝えなければルークが危険かもしれない。だと言うのに、ティナが待ったを掛ける意図がわからない。
「情報伝達は迅速である程効果的ではありますが、不完全では意味がありません。寧ろ逆効果です。」
「不完全とは?」
「仮に魔法や真道具を封じられたとして、兵数で勝っていた旧帝国軍が及び腰だった事の説明になるでしょうか?」
「確かにティナさんの言う通りですね・・・」
ティナの意見にスフィアが同意する。敵の魔法や真道具を封じ、自分達は自由に使える。もしそうなら理解出来る。しかし学園長の説明では、自分達も使えないのではないか。そう捉えられるのだ。その根拠をスフィアが続けて説明する。
「私は先程『魔法を使えないルークに投石や弓矢で集中攻撃』と言いました。これは相手も同じ条件という仮定の上での発言です。そして学園長も肯定しましたが・・・少し躊躇いがちだったでしょうか。」
「私もそう思いました。ですからこの場合、正しいですがそれだけではない、と考えるのが適切ではありませんか?きちんと確認してからの方が良いですし、まだ聞いていない秘密があるかもしれません。」
「そう言われると・・・」
ティナの意見に、カレンは少し早計だったと思い始める。そこへ畳み掛けるようにティナが補足する。
「それに駆け付けたカレンさんまでもが窮地に立たされては意味がありません。向こうの状況によっては、ルークの足を引っ張る恐れもあります。今回ルークは油断も慢心もせず、全力で真正面から向かいました。言うならば、本気のカレンさんが向かったようなものです。心配し過ぎだと思いますよ?きちんと情報を整理してからでも遅くはない。そうは思いませんか?」
「・・・ティナの言う通りかもしれませんね。」
カレンが向かったようなもの。つまりルークが窮地に立たされていたなら、応援に向かったカレンも窮地に立たされる恐れがある。カレンとしても自身に置き換えてみれば過保護に思うし、場合によっては邪魔に感じるかもしれない。そう考えたからこそ、否定は出来なかった。
「確認すべき事はまだ有ります。先程、大規模な設置型の魔道具とおっしゃいましたが、それが有るのは学園都市のお話ですよね?王都にも有るという事ですか?それとも国全体を覆い尽くす程の代物でしょうか?」
「流石に幾つも有る訳ではないし、当然そこまで広範囲に及ぶ威力の魔道具は存在せん。」
「では、学園都市から遠く離れた位置にまで効果が届くような魔道具だと?」
「違う。設置した場所を中心にして、そうじゃな・・・王都よりも少し広い範囲を覆うと言った所じゃろう。」
「「「「「?」」」」」
誰にでもわかる程の明らかな矛盾。元々は学園都市が安全だという根拠についての説明だった。つまり複数存在しないと言う以上、その魔道具は学園都市になければならない。だと言うのに、何故王都が出て来るのか。その理由はある意味衝撃的なものであった。
「・・・はぁ。愚かな王というのは、何も今に限った話ではない。長く続けば、それなりに現れるものなんじゃよ。」
「えぇと、つまり・・・過去の王が無理やり持ち出した、と?」
「「「「「え?」」」」」
「そう聞いておる。」
「問題ではありませんか?」
「大問題じゃな。私の首ひとつで済めば良いのじゃが・・・」
ティナの言葉に誰もが耳を疑う。世界中の王侯貴族が集う学園都市。彼らの安全確保の為に用意されたはずの魔道具を、愚王が勝手に持ち出したと言うのだ。この話が公になれば大問題。関係者の糾弾は免れないし、場合によっては戦争である。下手をすれば学園関係者も処罰の対象となるだろう。だがこれを否定するのは意外な人物だった。
「いえ、その辺りはどうとでも言い逃れ出来るでしょう。」
「・・・何じゃと?」
「私は通いませんでしたが、それでも貴族の子息を預ける以上はしっかりと学園都市についても調べました。過去の記録や文献にも全て目を通していますが、そのような記録は見た覚えがありません。つまり学園都市の魔道具がどうなろうと、公的に責める事は出来ないという事です。」
「その通りじゃが・・・」
「旧ミリス公国と帝国にそのような記録が無い以上、その魔道具が問題になる事はないはずです。まぁ、その他の国に無いとは言い切れませから、学園都市の記録を調べてみないと断定は出来ません。ただ言えるのは、王の力が及んだ事を勘案するに、責任の所在は学園そのものではなく都市の方でしょうね。」
学園そのものはミーニッツ共和国から独立している。どちらかと言うと、世界政府側だろう。そんな学園に対し、一国が強権を発動する事は出来ない。学園所有の魔道具を接収する事は不可能であるし、そんな事をすれば世界中を敵に回す。その事実を考慮した結果がスフィアの言である。
ホッと胸を撫で下ろす学園長だが、それも束の間の事。
「そういう事であれば、学園長が秘する理由にはなりませんね。取引には弱いでしょうか・・・。」
「っ!?」
「旧帝国軍が及び腰だった理由についてもお答え頂いておりません。」
「それは・・・」
スフィアに突き放され、ティナにまで追い打ちを掛けられる。洗いざらい打ち明けるのが取引条件でない以上、出来る限り情報を秘匿したい学園長。勝ち目は無いものの、スフィア1人ならば被害は抑えられる。ルビア不在の内に取引を終えてしまえば――そう考えていた学園長の誤算。
それはティナが、ここまでやり手だと知らなかった事だろう。
330話 侵攻18
330話 侵攻18
一方その頃――
政務に励むスフィアの手が止まる。今日は訓練する雰囲気ではなかった為、全員が地下室へと集合していたのだが――何人かがスフィアの様子に気付いて顔を向けた。
「・・・学園長。昨晩、学園都市が魔物の襲撃に遭ったようです。」
「っ!?」
「世界政府が派遣した兵士約2000名の内、死者約100名、負傷者は重軽傷合わせて400名以上との事です。」
「・・・・・。」
「保って今日明日、といった所でしょうか?」
「・・・・・。」
「帝国が地下通路の出入り口を封鎖している為、利用者に混乱が広がり避難に遅れが出ているとか。魔物が学園都市内部に入り込むようであれば、各国が地下通路の利用を禁止するでしょう。それだけではありません。賠償問題にまで発展するでしょうね。」
「・・・何が言いたい?」
淡々と事実を述べるスフィアだが、本心は別の所にある。そう感じた学園長が聞き返す。
「数日掛けて避難した者達が無事に受け入れて貰えると良いな、と心配しただけですよ。」
「どういう意味じゃ!?」
「難民の受け入れに関し、帝国は一切言及していません。いないのですが、いいえ、言及していないからこそでしょうか。難民を受け入れる事は、帝国と敵対する事に繋がるのではないか。そう考える国が無いと良いですね?と考えた次第です。」
「なんじゃと・・・」
驚愕する学園長に、冷徹な笑みを浮かべたスフィアが追い打ちを掛ける。
「王都陥落となれば、まずは帝国に対する賠償となります。その後で、避難民が押し寄せた各国に対して賠償を支払うだけの余力が残っているでしょうか?」
「あ・・・」
「只でさえどの国も厳しい状況でルークを敵に回すはずもなく、帝国に回すだけの賠償も期待出来ない。余程優しい国主でもなければ、無条件で受け入れるような真似はしない。そうは思いませんか?」
「・・・・・。」
敵を匿ったな?そうルークに言われれば、相手は謝罪するか敵対するかの二択である。国同士の謝罪の場合、ただ頭を下げて済むような問題ではない。難民受け入れは人道的な配慮だが、全ての国が人道的な配慮をするとは限らない。特に今回の場合、皇族に手を出された帝国は充分な根回しを済ませている。帝国側に落ち度が無い以上、自分達から手を出す事など出来ないのだ。
「心配ではありますが、打開策が無い訳でもありません。」
「な、何じゃ!?」
「帝国が事前に通達すれば良いのですよ。難民の受け入れに関して、帝国は一切関知しないと。」
「っ!!」
「まぁ、しませんけど。」
「・・・・・。」
好きにすればいい。そう帝国が言えば済むと聞き、学園長の表情が明るくなる。だが次の瞬間、スフィアの冷酷な一言で再び沈んでしまうのだった。だが学園長も気付く。
「・・・どうすれば良いのじゃ?」
「帝国にとって利益となる取引であれば、それもやぶさかではありませんね。」
「・・・私が出し渋っておる情報が望みと言う事じゃな?」
「どうでしょう?」
学園長が頑なに黙り込むだけの秘密。だがそれが本当に帝国の利益に繋がるかは、今のスフィアにはわからない。だからこそ明言を避けたのだ。
実際は無意味な情報でも構わない。帝国が難民の受け入れさえ拒んでいれば、ルークの怒りを買う恐れはないのだから。好きにすれば良いとは言っても、難民の中に犯人が居た場合は受け渡しを要求すれば良い。態とそういう態度をとる事で、スフィアは手札の価値を一層高める事に成功したのだ。学園長の情報が価値の低い物だった場合、さらに搾り取ってやろうと考えて。
「・・・学園都市があの場所に作られたのは、安全が保証されておったからじゃ。」
「どういう意味です?」
「何時の世も、人にとっての驚異は人なんじゃよ。どういう原理か、魔物が溢れる事のない魔の森によって背後は守られる。この上ない立地と言えるじゃろう。」
「それは帝都にも言える事ですね。ですが正面はどうするのです?」
「その悩みを解消するのが、大規模な設置型の魔道具じゃった。」
「「「「「?」」」」」
学園長の説明では、肝心な部分が伝わらない。だからこそ、その場に居合わせた者達は揃って首を傾げた。
「酷く燃費の悪い魔道具じゃが、その効果は絶大でな・・・一国の軍隊を相手にする事も可能な代物じゃよ。」
「どんな魔道具なのです?」
「あらゆる魔法や魔道具を封じる魔道具じゃ。」
「「「「「はぁ!?」」」」」
「正確には、大気中に集められた魔力を霧散させる代物じゃな。大気中じゃから、人体に害は無い。じゃが魔法も魔道具も使う事が出来ん。いいや、使っても直ぐに掻き消えると言うのが正しいじゃろ。」
「つまり・・・意気揚々と攻め込んだ所で、魔法を使えないルークに投石や弓矢で集中攻撃という訳ですか?」
「まぁ・・・そうじゃの。」
「「「「「っ!?」」」」」
単身で一国の軍隊を相手に出来るのは、圧倒的なまでの魔法に依るもの。それを知る者達が言葉を呑む。すぐに転移で駆け付けようとしたカレンだが、ティナと視線が合った事で何故かその行動を中断したのだった。
329話 侵攻17
329話 侵攻17
翌朝、ルークの姿はエリド村にあった。朝食を終えて一息ついた頃という、少し遅い時間帯。本日の政務が滞るのはマズイという体で、書類がある程度揃うのを待ち全て持参した格好だ。
「――と言う訳で、スフィアには此処で執務をして貰いたい。」
「・・・貴族絡みの案件が大半を占めているのは何故でしょう?」
「・・・偶々、じゃないかな?」
「・・・はぁ。わかりました。」
「・・・よろしく頼むよ。」
何となく事情を察したスフィアは、それ以上追求する事なく了承した。ルークとしても、何を言っても藪を突く事にしかならないと判断し余計な弁解はしない。単に押し付けただけなのだから、弁解の余地も無いのだ。
「それで、カレンはどうする?」
「どうすると言うのは?」
「見学に来るのかって意味だけど?」
「やめておきます。スフィアが受け持った政務の内容如何で、城へ赴かねばなりませんから。」
「そうか。悪いけど、カレンもよろしく頼むよ。」
急ぎ処理しなければならない案件に備え、スフィアの傍らで待機すると告げるカレン。貴族絡みの案件は時に迅速な処理を要するとあって、呑気に見物してなどいられない。その辺の機微に疎いルークだが、カレンの言葉に認識を改める。素直に謝罪を口にしたルークに、カレンは頷き返したのだった。
引き継ぎを済ませたルークは、アイテムボックスから美桜を取り出して腰に差す。それを見ていたナディアが疑問を口にした。
「武器は必要ないんじゃないの?」
「ん?いや、手加減するには必要だよ。」
「手加減?・・・するの?」
自重しない。昨日そう告げたばかりだと言うのに、それを翻すような発言に噛み付く。だがルークの説明は、言われれば納得の行くものだった。
「そういう意味の手加減じゃないから。何から何まで、本気で壊せばいいってもんじゃない。最低限、要職にある者達の首級は必要になるだろ?」
「それはわかるけど、それと武器に何の関係があるって言うのよ?」
「あぁ・・・今のオレだけど、力を持て余してる状態なんだ。」
「えぇ。・・・で?」
「どんなに手加減しようとしても、魔法も打撃も・・・跡形も残さず消し飛ばす自信がある。」
「は?」
「首級が必要となった時、肉片を集めても人物の特定なんか不可能だろ?それともナディアが復元してくれるのか?」
「む、無理!」
近付きたくもない難解なパズルを想像し、ナディアは全力で後退った。辛うじて頭蓋骨ならば組み立てられるかもしれないが、そんなものがあっても人物は特定出来ない。そこまで進んだ文明でないし、アンデッドを研究する魔女と噂になるかもしれない。科学とは、少しずつ進歩しながら浸透して行くのがベストなのだ。だがそれも、この世界には当て嵌まらないとルークは考えているのだが。
「それじゃあ何かあれば昼頃来るけど、無ければ夕方って事で。行って来るよ。」
「えぇ、わかりました。」
全員に見送られながら、ルークはミーニッツ共和国の王都近郊へと転移する。本来ならば人通りの多いその街道も、今は無人であった。だからこそ、ルークはいきなり街道へと転移したのだが。
「さて、まずは王都前に並んだ兵士達を・・・居ない?」
旧帝国の時と同様、王都の外でルークを待ち構えているものとばかり考えていた。だがルークの視界には兵士の姿が写ってはいない。これは流石に予想外だった。
「どういう事だ?まさか、地下通路の出入り口で待ち構え・・・いや、防壁内部に大勢の気配があるな。オレが近付いた所を蜂の巣にしようって作戦か?」
ある種の常套手段とも言える迎撃体勢なのだが、相手がルークでは意味を為さない。まだ王都の防壁までは2キロ以上離れているが、近付かねばならない理由も義理も無い。
「昨日と違って、小細工の必要も無いしな。少し派手に行こう。」
そう呟くと、ルークは頭上に特大の火球を浮かべた。距離があり過ぎて精密射撃は出来ないが、的が大きい為そこまで狙いを付ける必要も無い。もし狙いが外れても王都内部に着弾すれば良いと考え、防壁の若干上側を狙って撃ち放つ。だがその後の光景は、ルークを驚かすのに充分であった。
「なっ!?火球が消えただと!?」
目算で防壁の100メートル手前。突如として特大の火球が掻き消えたのだ。何かに防がれた訳でも、相殺された訳でもない。いや、この距離では見逃したのかもしれない。そう考えたルークは一気に距離を詰める。
「この距離なら見逃す事は無いだろ。」
王都まであと1キロの距離に立ち、先程と同規模の火球を今度は3発連続で撃ち放つ。今度は目を凝らし、僅かな異変も見逃さないよう注視する。だが結果は変わらない。
「・・・やっぱり消えたな。何かしたようにも見えなかったが・・・いや、既に何かしてると考えるべきか。」
兵士の姿は無い。だが通常とは異なる方法で、準備万端待ち構えていたのだろう。そう結論付けると、どう攻略するか思考を巡らすのだった。
328話 侵攻16
328話 侵攻16
自重はしないと宣言したものの、考えなしに知識を広めるのは別問題。万が一異世界転移組が文明テロを起こしたとしても、それは面倒を見ているシルフィ達の責任。彼女達が何とかするだろうと思うしかなく、ルークに出来るのはこの場の面々に釘を刺す事だけであった。
「まぁオレ達に言えるのは、迂闊に知識をひけらかすのは控えようって事だけだ。・・・相当脇道に逸れたから話を戻そう。とにかく、オレは今後一切自重しない。だからみんなには後始末を頼みたいんだ。まずは責め滅ぼした後の隣国について、かな。詳しくは事後の相談になると思うけど。」
「その事で聞いておきたい事、伝えておきたい事があるのですが・・・」
「ん?」
「『枷』とやらを外した事は聞きましたが、それでカレンさんを圧倒出来る程の力が得られるとは思えないのですが。要は7割増しですよね?」
「その事か・・・10年。」
「はい?」
「10年間、あらゆる力を常に封じて来た訳だけど・・・封じるってどういう意味だと思う?」
「抑え込む、ですか?」
「まぁそうなんだけど、わかり易く魔力に関して言えば・・・水瓶に蓋をするように思っていないか?」
「えぇ、まぁ・・・」
ルークの指摘が正しかったのか、スフィアは素直に頷く。しかしルークは笑みを浮かべた。
「なら肉体的な力は?」
「え?それは・・・負荷を掛ける、でしょうか?」
「そう、負荷だ。言い換えるなら、その分の重りを全身に装着しているようなもの。・・・厳しい訓練だろ?」
「「「「「まさか・・・!?」」」」」
四六時中負荷を掛けてのトレーニング。常に一定の重さではない、全力に対して常に一定の割合なのだ。ルークの力が増えれば、その負荷も同じように増える。
「ある程度体が成長してしまうとその効果は低くなるけど、幼少期は爆発的に増える。オレの場合は偶然その期間だった事で、劇的な効果を生み出した訳だ。出来る事なら、ずっと力を封じたままでいたかったんだけどな・・・。」
「では・・・例え誰かに敗北しそうな時も・・・力を封じて、抑えていたと言うのですか?」
衝撃の事実に、カレンが動揺しながらも問い掛ける。地球では『子供は何故疲れないのか?』という論文が発表されているのだが、ルークはそこまで説明する気がなかった。
「う〜ん、それに関しては前提条件が違うから何とも。」
「前提、条件ですか?」
「そもそもオレにとっての敗北と、カレンの言う敗北は違うんだよ。カレンの敗北は、文字通り勝負に負けるって意味だろ?」
「・・・ルークは違うと言うのですか?」
他にどのような意味があるというのか。理解の及ばないカレンの疑問は当然だった。
「オレにとっての敗北は、オレやみんなに取り返しのつかない状況が訪れる事・・・つまり重大な傷害とか死だな。それさえ回避出来るなら、特に勝敗には拘らない。」
「自尊心や誇りはどうなのです!?悔しくはないのですか!?」
「それでティナやみんなの腹は膨れるのか?」
「・・・・・。」
「別に負けて悔しくない訳じゃないけど、それはその後に活かせるかどうか。自分自身の心の問題だろ?目先の勝利に焦って、大事な場面で大切な人を守れない状況にだけは陥りたくないんだよ。」
「そ、そんな・・・」
あまりの価値観の相違に、カレンは俯いて黙り込んでしまう。これ以上カレンが会話に加わる事は無いだろうと判断し、スフィアはそっとしておく事を選択した。
「それでは、伝えておきたい事の方を。実はミーニッツ共和国には、旧帝国が攻めあぐねた秘密がありそうなのです。何とか学園長から聞き出そうとはしてみたのですが・・・」
「・・・・・。」
険しい表情のスフィアが学園長に視線を向けると、学園長は無言でそっぽを向く。そんな彼女の様子を眺め、ルークは吐き捨てるように告げる。
「言いたくなければそれでいいさ。と言うか、元々聞くつもりもない。仮に聞き出せたとしても、オレには言わないでくれ。」
「・・・え?」
「事前に通達したように、誰とも交渉はしない・・・温情を与える事も、容赦もしない。立ちはだかる者は真正面から叩き伏せる。学園の為とか民の為とか、誰かの為とか・・・オレには一切関係の無い話だ。そもそも、充分譲歩したつもりだしな。犯人が名乗り出る猶予も、民が逃げる時間も与えた。これ以上を望むのなら、それに見合った誠意を見せるのが筋だろ?」
「それはルークの言う通りですけど・・・」
「自重しないと宣言した以上、敵に容赦して自ら危機を招くなんて愚かな真似を犯すつもりもない。危害を加えようとする奴は、反撃の機会を与えずその場で確実に息の根を止める。」
「それは相手の事情や実力も確かめないって事か?」
武を修めるアスコットにとって、ルークの言い分は納得の行くものではなかった。だがそれも、彼とルークの前提条件の相違によるもの。
「確かめるって、一体何の為に?」
「何の為って・・・相手にだって事情があっての事かもしれない!それに自分の実力がどの程度なのかを知るには絶好の機会かもしれないだろ!?それに相手の技から学ぶ事だってある!」
「父さんは相手に事情があれば、例え母さんを殺されてもいいのか?」
「そ、そんな訳ないだろ!」
「それに父さんのは武術家の考えであって、オレには当て嵌まらない。」
「何?あれ程の技や実力がありながら、それはどういう意味だ?」
前提条件と言うより、決定的な勘違い。これはアスコットに限らず、この場に居合わせた全員に言える事であった。唯一の例外はティナ。しかし彼女は口を噤んだままだった。
「オレとティナ・・・シュウイチとユキの技は、人を殺す為の技だ。見せびらかしたり、誰かと競う為のものじゃない。」
「・・・・・。」
「相手に実力を出させる事なく、確実に息の根を止める。それだけに特化した、只の殺人術だよ。加えてオレに関して言えば武術家なんかじゃない。そもそも今のオレは皇帝だ!」
「なっ・・・」
自分達の価値観を押し付けるな。そう言われてしまっては、何も言い返す事が出来ない。1人冷静なティナだけは「違います!料理人です!!」と言い掛けて飲み込んだのだが――単なる蛇足である。
「また話が逸れたけど、学園長の事は放っておけばいいさ。ユーナに言われて助けはしたが、これ以上やり取りするつもりはない。協力するもしないも本人の自由だ。」
「・・・・・。」
「旧帝国やネザーレア、フロストルの時とは違う。今回からは最初から最後まで全力だ。慢心も油断もしない。明日中にはリノア達も連れ帰れるよう努力するから、心配せずに待っててくれ。」
「・・・わかりました。」
自信満々に告げたルークに、スフィア達は笑顔でそう答えた。この後、あまりにも話が逸れ過ぎて貴族とのやり取りをスフィアに頼み忘れ、1人頭を抱える皇帝の姿があったのは余談である。
327話 侵攻15
327話 侵攻15
賑やかな晩餐が終わり、一息ついた所でルークが疑問に思っていた事を口にする。
「それで、カレンがオレを夕食に誘った本当の理由は?」
「え?」
「単にみんなで食事を摂ろうと思ったから、ってだけじゃないよな?」
「・・・それだけですよ?」
「・・・そうか・・・ならいいんだ。」
真っ直ぐな性格だが、別に駆け引きが全くの苦手という訳でもない。カレンも感情を表に出さない程度の誤魔化しなら出来る。言えない、言いたくない内容なのかもしれないと判断し、ルークはそれ以上の追求を諦めた。
これだけのメンツが揃った状況で、やましい秘密を抱え込んでいるとも思えない。いくら夫婦と言えど、秘密の1つや2つはあるだろう。自分や他の嫁達を裏切るような真似さえしなければ、別に知らなくとも構わない。ルークはそう考えていた。
他に聞きたい事は無さそうだ。そう感じたカレンが質問を投げ掛ける。
「私も聞きたかった事があります。私に殺気を向けたのはどういう意味だったのでしょう?」
「ん?あぁ、あれか。教育と言うか、まぁ指導かな。斥候と言うのは何も相手との実力が拮抗している場合や、全くの未知数だった場合に限った事じゃない。例え格下であっても、気付かれたと思ったら即座に引くべきだ。」
「それは――」
相手がルークだったから。そう言い掛けたカレンの言葉に被せて、ルークは説明を続ける。
「オレ達には現時点でも女神カナンやエリド達という、一筋縄ではいかない敵が居るんだ。機会があるなら、日頃から訓練を想定して動くべきだと思うぞ?今回の黒幕がそのどちらかという可能性だってある。オレが相手だからと気を緩めるべきじゃないさ。」
「私は気を緩めてなど――」
「それなら尚更だ。単独で動くなら一層慎重に行動すべきだよ。それとさっきも言ったように、責めてるんじゃなくて指導みたいなものだから。今後に役立ててくれればいい。」
「・・・わかりました。」
誰かに諭される機会が少ないだけに、カレンの胸中は穏やかではない。だが彼女は感情を押し殺して了承した。
「さて、それじゃあ今後の予定を説明しておこうか。」
不満はありそうだが、カレンが納得した事で話題を変える。
「本当は時間を掛けてジワジワと追い込むつもりだったけど・・・気が変わった。」
「「「「「?」」」」」
「もう自重はしない。出し惜しみせず、全力を以て真っ向から叩き伏せる。つまり・・・明日、ミーニッツ共和国の王都には地図から消えて貰う。」
「「「「「っ!?」」」」」
「あの・・・本当に自重していたのですか?」
衝撃的な発言に全員が息を呑む。だがある程度の予想が出来ていた事で、当然の疑問を口にしたのはスフィア。
「自重していたさ。だから力を封じていただろ?それに異世界の知識も、極力見せないようにしてきたつもりだ。その辺はティナが一番良くわかっていると思うけど。」
「はい。技術的な面は当然の事ながら、特に気になっていたのは・・・料理です。」
「あぁ、そうだよな・・・。料理は科学と呼ばれる事もあるから、下手な物を作る訳にもいかなかったし。」
「その・・・科学?と呼ばれる技術は、伝えられない程危険な物なのですか?」
ルークが広める事に二の足を踏むとあって、物騒だと感じたスフィアが疑問を投げ掛ける。だがルークから返って来たのは意外な答えだった。
「いや、科学も突き詰めれば危険ではあるけど、この世界じゃ誰でも使える魔法や真道具の方が危険だと思うよ。」
「ならどうして?」
「オレが心配したのは、この世界のバランスが崩れる事かな。」
「どういう事?」
「フィーナやナディアだけじゃなく、みんなも疑問に思ってるみたいだけど・・・そう、だな。例えば料理や掃除、洗濯なんかにも魔法を使う訳だ。それが魔法を使わず、ある程度勝手にしてくれる道具が出来たらどうする?具体的には勝手にお湯を沸かしたり、衣服を洗ってくれる訳だ。料理も一定の火加減を維持したりだとか。」
「勿論使うわよ。」
ルークの質問に真っ先に答えたのは、ほとんど魔法が使えないナディア。だがそれは聞く前からわかっていたため、ルークの視線は他の者達に向けられていた。
「そうですね・・・作業に付きっきりである必要が無くなるのでしたら、誰もが利用するかもしれません。」
「それによってどうなる?」
「どう・・・?」
「魔法を使わなくて良くなるんだから、便利になるでしょ?」
「そう、そこだよ!」
「「「「「?」」」」」
フィーナの答えが求める物だったのか、ルークが指をさす。だが理解出来る者はおらず、誰もが首を傾げた。
「便利になるってのは、最初の内はいいかもしれない。だがそれによって魔法を使う機会が減る訳だ。生活にしか魔法を使っていなかった者は、魔法を使う機会が無くなる。それって、日頃から使われる事で維持出来ていた技術が、使われなくなる事で廃れて行くんだよ。数年、数十年先は良くても・・・」
「数百年先は、魔法を使えない者が現れる・・・?」
「「「「「っ!?」」」」」
「魔物が跋扈する世界で、魔法が使えないのは致命的。そうなると今度は、更なる科学技術の発展を求めるだろう。それは徐々に自然を蝕み、取り返しのつかない事態を招く・・・かもしれない。」
地球の環境問題を思い浮かべながら説明を行うルーク。だが確実にそうだと断言出来ないのは、この世界で何が起こるのかは知識に無い為であった。
「自然を蝕むと言うのは・・・住処を追われた魔物がどのような行動を起こすのか、予測がつかないという事ですね。」
「精霊も数を減らすでしょうね。いいえ、もしかすると精霊の怒りを買う恐れだってあるわ。」
「その辺はその時になってみないとわからない。只1つ言えるのは、そうなった場合に魔法が使えない者達が居るのは非常にマズイって事だ。」
魔法が使えなければ科学兵器に頼らざるを得ない。だが相手は強力な魔物となれば、当然威力を求める必要がある。結果、さらなる環境破壊が起こるという負のスパイラル。精霊に化学兵器が通用するかルークにはわからない以上、戯れでも手を出すべきでない事だけは言い切れる。
だがここで、静かに耳を傾けていたティナが根本的な問題に触れた。
「ですが、そもそも・・・そこまで急速な発展が可能でしょうか?」
「確かにそれもそうですね。ルークが言う程の高度な知識を持ち合わせた者など、この世界には居ないでしょうし。」
「いや、居るだろ?」
「・・・まさか、ルークが広めるつもりですか?」
断言したルークを見つめ、恐る恐るといった様子でティナが尋ねた。だがルークは頭を振って否定する。
「流石にオレは広めたりしないさ。でも、女神カナンの被害者達が居るだろ?」
「「「「「あっ!」」」」」
「ですが、彼女達はそれ程高度な知識を持ち合わせてなどいないと思うのですが・・・」
「まぁそうだろうな。でも現役の学生に、社会人だ。一通りの一般教育は受けている。伝える相手次第にはなるけど・・・ある程度の公式は覚えているだろうし、見た物を口にするだけでも2、300年は進んでしまう恐れがある。」
下手に抑圧すれば、反動が怖い。それ程、人の好奇心とは恐ろしい物なのだ。しかしルークが危惧しているのはもっと別の事。
「それよりも、オレは女神カナンの被害者が増える事を心配している。それが専門知識を持ち合わせている人物だった場合、与える影響は爆発的に拡散するはず。前例が出来た以上、今後も無いとは言い切れないだろ?」
「「「「「っ!?」」」」」
因みにルークは専門知識から雑学まで、圧倒的なまでの情報を保有しているのだが――この場でそれを口にする事は無かった。
326話 侵攻14
326話 侵攻14
ティナから普段のニコニコ微笑む表情が消えた事で、全員が固唾を呑む。視線を集めたティナは、逸していた視線をカレン達へと戻す。
「・・・対応策を相談する前に、済ませておかなければならない事があります。」
「えぇ、時間が掛かりますからね。先にルビアさん達を――」
「昼食の支度をしましょう!」
「「「「「・・・・・」」」」」
議論が白熱した場合、ルビア達がルークと鉢合わせするかもしれない。そう考えたスフィアの提案を遮る形で、ティナが欲望を丸出しにした。本人は至って真面目なのだが、他の者達は呆れて物が言えない。
「どうしました?」
「・・・何でもありません。」
「?」
皆の様子がおかしい事に気付き、ティナが首を傾げる。だが説明する気も失せたスフィアが首を振ると、訳がわからないティナはさらに首を傾げたのだった。
大人数ということもあって、賑やかだが効率良く昼食の準備を済ませる。その後全員が――特にティナが腹を満たし、この場に居ない事になっている者達を全員アームルグ獣王国へと送り届ける。何故帝国ではないのかと言うと、今の状況では獣王国の方が安全だからである。
帝国からは相当な距離があり、ルビア1人を狙うには労力が要り過ぎる。加えて獣人は気配に敏感で、嗅覚や聴覚にも優れている。守るにはうってつけの場所なのだ。オマケにルビアが居る事で、ルークに敵視される心配が無い。ルビアが安全な限りはWin-Winの関係とあって、警護にも気合が入る。
ルビア以外に関しても『後で危険な目に合いました』では示しが付かない。下手をすればルークの怒りの矛先が向くとあって、ルビア同様の厳戒態勢である。
居るべき者達が居る、本来あるべき姿になった事で、漸く新たなルーク対策について話し合うティナ達であった。
一方その頃――
「こっちの・・・貴族家同士の婚姻について、皇室に伺いを立てる書状。これはまぁ、なんとなく理解出来る。貴族同士のしがらみなんかがあるんだろうさ。問題はこっちだ。『――カーネル男爵家のご令嬢は、心に決めた方が既にいらっしゃるのでしょうか?』・・・知るか!誰だよ!!」
帝国城内の執務室には、書状を放り投げ荒ぶる皇帝の姿があった。
処理や決済の必要な政務を終わらせ、貴族等から送られて来る書状に目を通していたのだ。嘆願や陳情等、割と重要な内容の物が多いとあって、確認しない訳にはいかない。しかし能力的にはスフィアに勝るルークも、致命的な弱点があった。貴族や役人に関する知識が皆無なのだ。
実はルークが匙を投げたこの書状も、貴族同士のしがらみあっての内容なのだが――今のルークにしてみれば、親しい友人からの相談としか思えない。一国の主としては落第である。自身もそれを痛感している為か、冷静になって愚痴を零す。
「・・・はぁ。四六時中カレンが貼り付いてれば大丈夫だろ・・・スフィアだけでも呼び戻すか?いや、それだと向こうの出方が変わってくる。それにカレンは真正面からの勝負なら強いけど、予想外の搦手で来られると後手に回る恐れがある。事前に想定して万全の準備を整えてたリノア達とは違って、カレンだけに任せ切りは流石にマズイ。」
比較的真っ直ぐな性格のカレンは、ある程度の搦手には対応出来ても、あまりにも複雑だと対処が遅れてしまう。単独ならばどんな搦手だろうと生還してしまえると信じているが、足手まといが居ては不安が残る。これはルークだけでなく、ティナ達も同意見だった。かと言って護衛を増やそうにも、信頼出来る実力者は嫁の誰かとなる。相手の狙いが絞れない以上、標的を増やすのは得策とは言えないのだ。
「・・・急いで返事を書かなきゃいけないもんでもないし、後でスフィアに頼むとしよう。」
あれこれ悩み抜いた結果、丸投げという結論に達したのだった。そうと決まれば、本日の執務は終了である。時刻は午後1時を過ぎた頃。規則正しい食生活のティナ不在という事で、昼食を後回しにした結果。思いの外、時間に余裕が生まれた事で、今後についての考えを改める。
「もう自重はしないと決めた事だし、いよいよ料理の方も解禁だな。」
スフィアが聞いたら卒倒しそうな事を呟き、腕を組みながら天井を見上げる。どうせ自重しても面倒に巻き込まれるのだから、やりたい放題して巻き込まれた方が精神衛生上良いだろうと考えての事。そうして考えているのは、何を作るかという事である。
「う〜ん・・・決めた!手間暇の掛かるアレにしよう!!」
驚異的な身体能力と魔法で時短は出来るが、それでも量を作るとなると完成までに要する時間は地球と大差無いだろう。冷ましたり感想させたりといった工程ならば短縮可能だが、焼く時間は短縮出来ない。オーブンの大きさは決まっているのだから。流石のルークも、火魔法で絶妙な火加減を継続する余裕は無い。料理となると、他にも作業は山積みなのだから。
結局ルークは、スフィアやカレンの予想から大幅に遅れてエリド村を訪れる。あまりにも心配になったティナが何度もルークを呼びに行こうとし、カレン達が何度も総出で抑え込んだ事をルークは知らない。
(何だかみんな疲れ果ててるな?・・・訓練を頑張った証拠か。それなら頑張って作った料理を振る舞って労うとしよう!)
見るからに疲れ果てたカレン達に、見当違いな事を考えたのは当然だった。
振る舞われた夕食は、この世界の人々が食べ慣れた物。だがルーク監修とあって、そのレベルは高い。だが全員に衝撃が走ったのはデザートだった。
「な、ななな、何ですかコレは!?」
「全部色が違う!?」
「か、かわいい・・・」
主に女性陣の食い付きが半端ないのだが、ルークは若干申し訳無さそうに説明する。
「これはマカロンというんだけど、時間が無くて7種類しか作れなかった。小さくて悪いけど、人数も多いから――」
「おかわり!」
「・・・は無いから、みんな味わって食べるように。」
「ガーン!」
「「「「「・・・・・。」」」」」
ルークが配膳してから説明するまでの間に食べ尽くしたティナが絶望する。まだだれも口にしていないというのに、恐ろしいまでの早業である。誰が悪い訳でもない為、ティナを叱りつける者は1人も居ない。
総勢38名分、ティナの消費量を換算すると約50名分となる。それだけの料理をしながら、計266個ものマカロンを1人で作り上げるだけでも驚異的。誰も文句は言えないのである。
「美味しい!」
「じーっ」
「あまーい!」
「じーっ」
「サクッとしているのに、フワッとしているんですね・・・」
「じーっ」
「不思議な食感!」
「じーっ」
「あら?先程とは味が違うのですね!」
「じーっ」
「ティ、ティナ・・・?」
「じーっ」
「「「「「食べ難いわ!」」」」」
誰もが最初の1、2個に舌鼓をうったのだが、ティナの視線が気になりその手が止まる。マカロンを口に運ぶ度に顔を向けられては、とてもではないが食事を楽しむ事など出来ない。
流石に人数分をキッチリ作っているはずもなく、結局は見兼ねたルークがおかわりを出す事で落ち着いたのだった。
325話 侵攻13
325話 侵攻13
ほぼ全員が呆気にとられる中、スフィアは思考をフル回転させる。
「(少なく見積もって、とおっしゃいましたね?ルークが何処まで出来るかはその時になってみないとわからないと言う事。ならば今考えるべきは・・・)すみません、カレンさんに質問があります。」
「何です?」
「ルークはどうやって傭兵や冒険者達の命を奪ったのでしょう?」
「・・・・・。」
「カレンさん?」
カレンは上手く言葉を濁して説明を行ったのだが、スフィアの問い掛けに黙り込む。今嘘を吐いた所で、調べればすぐにバレる。どうやっても言葉では勝てない事を再認識し、迷った挙げ句正直に告げる事にした。
「・・・わかりません。」
「え?」
「推測は出来るのですが、確証が無くて・・・」
カレンは詳しく説明しなかったのではなく、説明出来なかった。暗にそう言っているのだ。
「推測でも構いません。教えて頂けますか?」
「・・・わかりました。恐らく合っているとは思うのですが、ルークは殺気を叩き込んだのだと思います。」
「「「「「え?」」」」」
「そ、それだけですか?」
「はい。それだけです。」
殺気を込めただけ。そう言われても到底納得出来ない。荒事がお手の物であるはずのエレナ達ですら、聞き間違いかと思ったのだ。戦闘などからっきしのスフィアが理解出来るはずもなかった。
「殺気で人が死ぬと言うのですか?」
「条件が合えば死にますよ?」
「条件、ですか?」
「えぇ。そうですね・・・例えば、目の前にドラゴンが現れたらどうなりますか?」
「・・・動けなくなります。」
「もう少し具体的な反応を答えて下さい。」
質問に対する答えとしては不十分。そこでカレンは具体的な答えを求めた。つまり肉体に何が起こるのかを考えさせようとしたのである。普通ならば経験の無いスフィアは答えられない。だが様々な体験談や物語で耳にした事を繋ぎ合わせ、想像を膨らませる。
「・・・身動きが取れず、声すらも出せなくなります。」
「それから?」
「その後は・・・・・体が震えるか、冷や汗が止まらな・・・え?」
「そうですね。つまり、先程の私です。」
「「「「「っ!?」」」」」
額が汗でびっしょりだった理由を知り、全員が息を呑む。つまり、カレンとルークはスフィアとドラゴンの関係に近かったと言うのだ。カレンの実力を知る者にとって、とても信じられるものではない。
「ある程度実力が拮抗していれば、殺気は耐える事が出来ます。ですが、実力差があると耐える事は難しいものです。」
「でも、カレンとルークの差はそこまでじゃないでしょ!?」
「そうですね。ナディアの言うように、スフィアとドラゴン程の実力差ではないでしょう。ですが、一般的な冒険者ならどうです?」
「それは・・・」
ナディアが答えられないのは、カレンと一般の冒険者でさえ、スフィアとドラゴンの差を上回るとわかりきっている為だ。それがルークとなると、赤ん坊かそれ以下と言わざるを得ない。
「スフィアの答えは一般的なものです。言い換えるなら平均になります。つまり、最悪の場合・・・命を落とす者も居る、という事です。そういう話を耳にした事はありませんか?」
「ありますが・・・作り話の類では?」
「強ちそうとも言い切れませんよ?心理的な負担というのは、無理をすれば命に関わります。身動き出来ず、声が出せない。酷ければ呼吸が止まるでしょう。体が震え、冷や汗が止まらない。鼓動が早くなり、最悪ショックで心臓が止まります。心理的な不調は肉体に現れるものです。今回の場合、子供がドラゴンの群れに遭遇したようなもの。急激な心理的負荷により、傭兵達の心臓が止まったのだと思います。」
「「「「「・・・・・。」」」」」
有り得ないとは言い切れない。納得させられた事で、誰もが言葉を失ったのだった。だが1人だけ異なる反応を見せた者が居た。
「カレンさんが殺気だけで済んだと言う事は、警告ではなく教育が目的だったのかもしれませんね。」
「どういう意味です、ティナ?」
「カレンさんは徐々に近付けたのですよね?」
「えぇ。」
「おかしくありませんか?いつ何処から敵が現れるかわからないのです。警戒するのであれば、態々範囲を狭める必要はありませんよね?」
「そう言われると・・・」
近付く事に必死だったせいで、不自然な点を見落としていたのかもしれない。カレンはそう思い始めた。
「ある程度接近した所で、突然範囲を広げられたらどうするつもりだったのです?」
「っ!?」
もっとも過ぎる指摘に、カレンが息を呑む。少なくとも、カレンが気付いた位置までは警戒範囲を広げられるのである。これが罠だった場合、カレンは対処が遅れていただろう。転移で逃げるという選択肢はあるが、確実に間に合う保証は無い。
「ですが今回の場合、そうせずいきなり殺気を向けられたのですから、何か別の方法でカレンさんの動きを把握していたのではないでしょうか?」
「そん・・・な・・・!?」
「・・・これは今後の対応を考え直す必要があるかもしれませんね。」
肉体、或いは神力だけでは説明出来ないような実力差がある。その事に戸惑いを隠せないカレン。もしティナの指摘通りなら、ルークとカレンの差は5倍どころの話ではない。10倍、もしくは数十倍の実力差があるかもしれない。
もしそうなった場合、ルークを止められる者が居ない事になる。それは嫁達にとって非常にマズイ状況とあって、珍しく食べ物以外で真剣な表情となるティナであった。